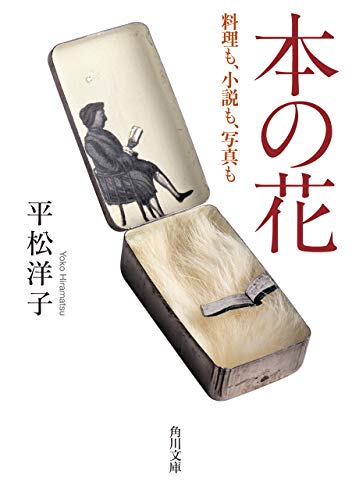平松洋子さんの書いた書評を集めた一冊。
読んだことない本がいっぱい出てきました。
P206
フェイスブックもブログもLINEもツイッターも一切合切なんにもやらないわたしだが、『辛酸なめ子のつぶやきデトックス』を読んで、滝に打たれたようなすがすがしい気持ちに。
「透け感とか、丈感とか、とりあえず何でも「感」を付ければ、洋服屋でナメられません」
「「打ち上げ」の反対で、ハーブティーや水を飲むストイックな「打ち下げ」という風習をはじめたいです」
脳内に生じた違和物質は、溜めておくと発酵のち腐敗したりする。むかしなら「ひとりごと」をブツブツ言う手があったが、アレが虚しい気持ちになるのは、けっきょく自分で自分を受け止めるしかないから。でもわたしたちには、その進化系、ツイートがある。どこかで誰かがフォロー、つまり「共有物」に変わる。ただし、世間ではちょっと厄介なことになっていて、ツイッター上でバトルの応酬が展開されることしばしばのようだ。余計なお世話だが(厄災の種まきは疲労のもとでは?)と気を揉み、(電話したほうが早くはないか?)と心配してしまうのだが、当事者にとっては一対一はつまらないのだった。
いっぽう、フォロー0人で始めたという辛酸なめ子のツイートは、その対極にある。テーマはアセンション(次元上昇)。つぶやきの相手を霊界とのつながりに設定してあるだけに、こころの吐露のピュア度が高い。しかも「自分の霊格」を高めようと、みずから啓示を公開してくれる。
「回転寿司のいいところは回っている寿司のエネルギーも吸収できるので3皿くらいで満足できることです」(二〇一二年二月十九日)
「最近、女性ホルモンが分泌されることを期待して、ひとり寝ている間アクセサリーを付けています。寝アクセサリー、はやるでしょうか」(二〇一二年四月四日)
でも、気を抜いていると、ぐさりと本質を突かれるので油断できない。
「昨夜どこからともなく聞こえてきたメッセージ「恋愛は、自分の心で遊ぶ行為」」(二〇一〇年七月十二日)
「中身のない女はダメだとよく言われますが、中身がありすぎる女もヤバいと思います」(二〇一〇年十月二十五日)
そもそもデトックス、出たモノに毒があるのはとうぜんなのだった。
金言箴言のオンパレード、厳選五百七十七個のツイートにはブラックな社会風刺もあちこちに。でも、あくまでも自身の霊格向上が目標だから、巷のツイートにありがちな自己顕示や宣伝、攻撃や批判の臭みがないところがものすごく爽快だ。あらためて辛酸なめ子に萌える。
人生の助け舟もいただけます。
「辛いできごとは、前世だと思ってしまえば大丈夫です」(二〇一一年五月十二日)
P276
虚を突かれた。
「治りませんように」
奇妙なタイトルにぽかんとして、しだいに混乱する。病気が治らないよう願う者など、いるはずがないではないか、と。
これは十年の取材にもとづく記録と思索を杖に、人間の生きる意味をもとめる一冊である。舞台は北海道の南、襟裳岬にちかい浦河町「べてるの家」。「べてる」は旧約聖書で「神の家」の意味だ。精神障害を患うひとびとの共同体として約三十年、現在のメンバーは約百五十人。介護や福祉事業、NPOなどを運営し、精神科医やソーシャルワーカー、家族らが支える。異色の存在として知られる活動の主体は、患者じしん。病気をわが財産と位置づけてつらい現実を受け容れ、社会との関係を保ちながら回復をめざす。「苦労の哲学」。これが「べてるの家」と深くかかわったジャーナリスト、斉藤道雄さんにもたらされたたまものだ。七年引きこもったのち浦河に来て二年目、統合失調症に苦しむ清水さんとの対話。彼女は言う。
「わたしがたとえば分裂病だとしても、そうでなくても、わたしがいまのわたしであることになんの変わりもなくて、そのことに対して違和感がないので、よかったなと思ってる」
治ることにしがみつかなくていい、病気のままのわたしが自分だから。そう思えてはじめて、生きるのが楽になった。「治りませんように」とは、自分との和解の言葉だった。
苦労すること、不安を抱くこと、悩むこと。それは負の感情ではなく、当事者である自分をだいじにすること―生きる手がかりを苦労のなかに発見してゆく筆致に、透明度と密度がある。・・・
回復のよりどころは、つまるところ言葉なのだ。患者みずから生みだした名言のひとつに「なつひさお」があるという。被害妄想や自傷行為のメカニズム(悩んでいる・疲れている・ひまで・さびしい・お金がない)を表現する一語には、ほのかなおかしみさえ漂い、人生への肯定をうながす。たとえいっときの通過地点だとしても、共通の言葉を分かち合って築いた理解は励ましの効力を発揮するのだ。
その中心にいるのは「治さない医者」を標榜する精神科医、川村先生である。とはいえ、むろん治さないのではない。医師が主導権を握らず、管理せず、選択のおおくを患者に委ねる。それは、医師も患者もどちらも「他人の価値に生きない」ための決意であり、苦渋や葛藤をも引き受ける果敢な治療に思われる。